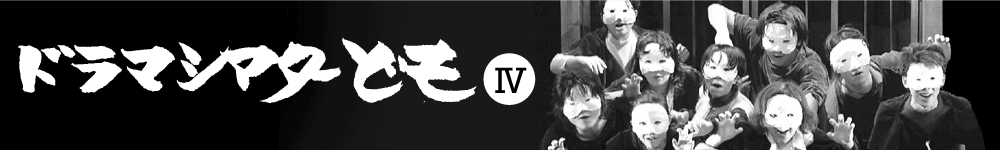はじめに
劇場とは
どもⅣを祝うパーティである人が次のような意味のあいさつをして、ハッとさせられました。
「ほかの劇団の人々は稽古場兼発表の場として自分の空間を持つことはあるが、どもさんの場合は、自分の芝居をやるだけの場所じゃない劇場づくりというのが最初からあったんじゃないだろうか」と。
劇場というのはいろんな人が入ってくる。ある意味で冠婚葬祭も含めて、本来の劇場とはそういうものだと思います。あまり意識してこなかったけど。
ドラマシアターどもは江別の顔であるべき江別駅前で、新たな一歩を踏み出しました。
ドラマシアターどもの『どもさん』夫妻紹介〜『どもさん』と『がまちゃん』

○安念智康(愛称:どもさん)
「ども」は高校時代の智康の愛称。
○安念優子(愛称:がまちゃん)
喫茶店を切り盛りし「劇団ドラマシアターども」の団員でもある。「がま」とは中学生のときに旧姓が水口だったのと、大きな赤いがま口をいつも持っていたので付けられた愛称。
どもとドラマ
ここではドラマシアターどものはじまり、支えて下さった皆様、挫折と復帰など数多くのどものエピソードを紹介しています。
ドラマシアターどものはじまり〜東京での挫折
 のちに「どもI(ワン)」と呼ばれる最初のどもは1981年7月にオープンしました。演劇で身を立てようと上京した青年が挫折して故郷に帰り、再起をかけたのがどもIでした。
のちに「どもI(ワン)」と呼ばれる最初のどもは1981年7月にオープンしました。演劇で身を立てようと上京した青年が挫折して故郷に帰り、再起をかけたのがどもIでした。
江別高校時代、どもさんは演劇に明け暮れました。芝居をやりすぎて授業に出ないから卒業まで4年かかったのです。教師が見るに見かねて『おまえはふつうじゃない。東京に行って芝居をやれ』と。それで東京の劇団に入ることとなりました。
土方与志・秋田雨雀記念青年劇場。大正年間に土方らが創設した築地小劇場の流れをくんだ劇団でした。また劇団に入って1年半ほどのちに中央大学に入学します。しかしときは70年闘争まっただ中。大学はロックアウトされ、まともな学生生活はできませんでした。
そんな中、東京に行って3年目のとき、どもさんはある大きなものに出合ったのです。
モスクワ芸術座が来ました。1日のアルバイトが千円、家賃が5千円のときにチケット代が5千円。社会主義リアリズム演劇の最高峰の、ちょっとかげりはoてはいたけれども、ゴーリキやチェーホフに育てられた俳優たちがごっそり残っていた。これを観たときに、日本のレベルはなんだ、子どもと大人じゃないかと思ったのです。
どもさんはもともとモスクワに行ってロシア文学をやりたいという願望を抱いていて、大学の第一志望も早稲田大学の露文でした。そんな青年がソビエトを代表する劇団と出合ったのですから感激しないわけはありません。そしてあまりのレベルの違いから、演劇にかける情熱はしぼんでしまいました。
3年いた青年劇場をやめて、そのあとの3年間は、どこかの劇団に入る気は全然ありませんでした。何をやったらいいのか、人生いかに生きるべきか、悩みに悩んでいました。今になって思えば、あのとき悩み抜いて良かったのだとどもさんは語ります。
劇団ほかい人群(びとぐん)との出合い
 江別に帰ったどもさんは塗料の会社に入り、開発局などに売り込むセールスマンになります。そして高校の演劇部でどもさんが4年目のときに1年生だったがまちゃんと結婚します。
江別に帰ったどもさんは塗料の会社に入り、開発局などに売り込むセールスマンになります。そして高校の演劇部でどもさんが4年目のときに1年生だったがまちゃんと結婚します。
どもさんが帰ってくる1年前に江別には川という劇団ができていました。農村青年と江別中心街の青年たちが合同した10人ほどの若い所帯でした。
稽古を見に行くと、芝居をやろうという雰囲気はあったので入団しました。でも若いから芝居よりは酒だとか男女の恋愛だとか、目標がそっちになっちゃう。芝居はブライダルセンターじゃない!がぼくの口癖でした。最初はがまんしていたけれども、どうしても合わなくて。がまちゃんと別れて東京に戻ろうかなとか、気持ちはぐちゃぐちゃに揺れていました。
そんなとき、どもさんたちにとって生涯で最も大きな出合いがあるのです。愚安亭遊佐さん率いる劇団ほかい人群との出合いでした。彼らはボロワゴン車に大人 6人、幼児1人、犬1匹と鍋釜を詰め込み、投げ銭で公演していました。まさに家々の門前で物をもらいながら流れ歩く「ほかいひと」そのもの。しかし芸のレベルは高く愚安亭さんの一人芝居は当時から高い評価を受けていましたが、18年後の1999年には文化庁芸術祭優秀賞を受章するなど多くの賞を受賞しています。どもさんはもちろん高レベルの芸に感銘はしましたが、衝撃を受けたのは芝居のテーマでした。
川の劇団員はぼくが代表になって30人くらいに増えていて、15人くらい引き連れて観に行きました。それはすごかった。レベル的に演劇の基礎がきちっとできていたからね。特に人生一発勝負はすごかった。愚安亭の母親の一代記だけれども、自分の生まれ育った下北から少しも外さないで母親の一代記という愚安亭しか見ていないことを下北弁という本人しか語れない言葉で語っていく。おまえは芝居をやって何をつくりたいんだと、舞台から突きつけられた気がしました。
それまで劇団川が取り組んできた芝居といえば「セールスマンの死」など東京から取り入れたものばかり。それが文化だと思っていました。また演出家志望だったどもさんは、名作は一字一句まちがっちゃいけない、へたな(台)本など書いちゃいけないという教育を受けていました。ただしそういう意識がある一方で、いつかは北海道の本を書くという漠然とした思いがあり、資料は集めていました。
ほかい人群の道内公演では白老町に1軒家を借りて拠点にし、知り合いのところを泊まり歩いていました。ところがその晩は泊まるはずのお寺で葬式が入り、急きょ白老まで帰るといいます。そこでどもさん夫婦は自分のアパートに泊まってもらうことにしました。もともとアパートには芝居関係者などが毎日のように寝泊まりしていたのです。初対面の夫婦が泊めてくれたことで、ほかい人群のメンバーは感激し、交流が始まります。そしてがまちゃんが、彼らの旅公演に3ヶ月間同行するのです。
「がまちゃんは一緒に芝居をやっていたんだけれど、ぼくとは経歴がちがう。それでプロとは何かを経験するために一緒に旅してこいと。ぼくが頼み込んで同行させてもらったんです」 下北半島、盛岡、東京、愛知…。旅は続きました。
「今から思えばいい人生修業たったと思うね。世界が大きく広がった。帰ってきたら、どもさんが会社を辞めていました」(がまちゃん)
幼稚園の教諭や保母を断続的にしていたがまちゃんが旅に出ている間に、どもさんは会社を退職し、自分の劇団を持って本気で芝居をやるつもりになっていました。
ドラマシアターはみんなの手で
たまたま見つけた野幌駅前のレンガ造り倉庫。そこで初代ドラマシアターどもが誕生します。それは喫茶店の名前であり、劇場の名前であり、のちに劇団の名前にもなっていきます。
「ぼくは大工仕事ができるわけじゃない。最初に手伝ってくれたのが劇団川の農家勢でした。彼らの仕事が忙しくなって来れなくなると、見るに見かねて親父やその友だち、弟たちが手伝ってくれました」
どもさんは4人兄弟の長男です。父親は農家の長男でしたが、跡を継がずに馬車追い、今でいう運搬業を営んでいました。江別は王子製紙の城下町として繁栄し、父親も羽振りのよい時代がありました。よく映画館に連れて行ってくれた、という子どものころの思い出がありますが、決して優しい父親ではありませんでした。
どもさんが東京での辛さに絶えきれず故郷に帰る決心をして、母親に伝えようと電話したとき、いきなり出たのが父親でした。
「東京を引き払おうと思って、と言ったとたん『バカやろう!』と頭から怒られて。『何て言って出ていったんだ!』と。東京に行くとき『河原者に育てた覚えはない!出て行け!』『ああ、出て行ってやる!』と言って出てきたんです。でも最後には、そんなに辛いなら帰ってこいと。やはり親だなと思ったね」
どもさんは北海道の開拓農家の5代目。しかも直系で本家筋の長男です。芝居に明け暮れて東京に飛び出し、絵にかいたような挫折を経験して故郷に帰ってきた。結婚しておとなしくサラリーマンを続けていたと思ったら、今度は会社を辞めて芝居に専念し新しい空間をつくるという。そんなどもさんですが、親兄弟は見捨てませんでした。
父親が道具一式を持ち込み、友だちも動員しての大工仕事。レンガ造り倉庫が店舗の形に改造されていきます。父親の安念清光さんはその1年後に亡くなります。58歳でした。
大工仕事の次に喫茶店や劇場の備品をつくってくれたのは、出合いの翌年、北海道に来ていた劇団ほかい人群の人たちでした。そのときのカウンターやテーブル、芝居用の木箱などは今に受け継がれています。